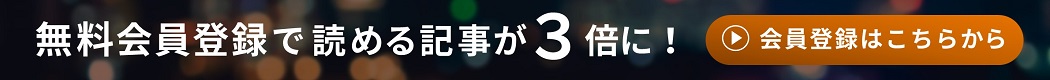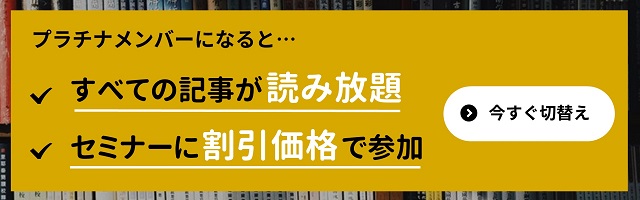2019/01/30
1/3ページ
イマ、ココ、注目社長!
第7回
「ゲームプレイ」と「ゲーム観戦」をさらに上位のエンターテイメントへ昇華させる!【前編】
- 注目企業
- 組織
- 経営
- 経営者インタビュー
――そういえば、『ウェルプレイド』という社名の由来はどういうところに?
谷田 当時、『ハースストーン』というデジタルのカードゲームがありました。『ブリザード』という会社が作っているアメリカのカードゲームなんですが、そのゲームがまだ日本に展開してくる前に、「すごく面白いから流行るかもしれない」と思いながら、うちの役員連中がむちゃくちゃハマっていた時期があったんです。ちょうどその頃に会社名を決めようという話になって、そのゲーム内で相手を称賛する言葉の中にあった「ウェルプレイド」から取ることにしました。その言葉に「プレイヤーを評価する世界を作る」という思いを込めたわけです。
そうしたら、その社名がきっかけになって、大きなチャンスをいただくことになりました。2016年の5月くらいに、『ハースストーン』の日本選手権みたいな大会を国内で開催することが決まり、それを手伝える会社を探しているという話を代理店さんから聞いたんですね。そこで、ブリザードさんに、「この会社名は御社のゲームをやるために作ったと言っても過言ではありません」、「今すぐ対戦していただいてもかまいません。僕たちは〝にわか〟じゃないです」というお話をしに行きました。実際、そのとき役員全員がアメリカサーバーのランクの上位2%以内に入っていましたからね。
――確かに説得力がありますね(笑)。
谷田 「このゲームがそこまで好きだからこそ選手のことも馬鹿にしないし、ゲームのことも理解しているし、ビジネスの話もきちんとできますよ」というところも含めての交渉が、結構うちの強みになっていて、そのときに、「じゃ1回チャンスをあげたい」と言ってもらって、そのお仕事をさせていただきました。日本選手権とか全国大会みたいなものの生放送と大会運営、要はそれをまとめていくことをちゃんとやった初めての仕事でした。この仕事がわかりやすい名刺になり、その後は、「ああそういうことができる会社なんですね」という認識が広がっていきました。
――そのときはお二人以外に何名かいらっしゃった?
谷田 当時社員はゼロです。会社は5人で立ち上げたので、役員には僕と高尾以外に3人いました。この3人はもともと別の会社の役員や社長をやっていて、要は、彼らのスキルとか、アセットが必要なときにはその都度貸していただく、という形で参画してくれていました。そのうちの一人、CTOのポジションの人は、今はうちにいます。
――CEOとCOOという役割分担は最初にスッと決まったんですか?
高尾 僕が前職の都合もあって後から合流する形になったので、最初は「谷田が社長、僕が副社長」という形でやっていました。そうしたら、数ヵ月後に谷田が「共同代表でよくない?」みたいな話をしてきたんです。僕は肩書きにこだわりはなかったけれど、「そういうことを代表の方から言うこともあるんだな」と驚きました。彼はそういうことが言える器なんですよ。僕は自分が代表になったことよりも、そういう提案ができる人と並列で仕事ができることが素直に嬉しかったし、面白いなと思いましたね。

この3年でeSPORTSプレイヤーへの社会的評価は急上昇中!
――さて、日本でeSPORTSが言われ出したのはわりと最近だと思いますが、今、eSPORTSのチームって何チームくらいあるものなんですか?谷田 自分たちで名乗ることで「チーム」と言えるのであれば……、
高尾 ほぼ無数にいますね。たぶん、一つの大学に1、2チームくらいはあるんじゃないでしょうか。
――テレビでも見たことがありますが、企業が支援している本格的なチームもあるようですね。
高尾 そうしたチーム自体は、以前からありました。特定のゲームタイトルにおいては、《日本の一位を決めた後に世界大会で勝負できる》という構図ができていて、例えば、一番有名なものの一つに『リーグ・オブ・レジェンド』がありますが、これは10年も前のゲームなので、そこで勝負できる体制を作りたいと思っているプロチームというのは、もう何年も前から存在しています。
それと並行して、海外のタイトルをプレイする環境もあれば、日本で生まれたゲームを一生懸命プレイする環境もある。この3年くらいでタイトルのラインナップがパソコンゲームに限らず加速度的に増えてきているので、要はそれに沿ったプロチームが必要だし、それに沿ったプロゲーマーも出てきたという感じですね。
格闘ゲームのプロも、出てきてまだ5、6年という状況の中で、やっぱり加速度的に人も増えています。僕がポイントになるなと思ったのが、レッドブルさんが『ストリートファイター』のプロゲーマーを、プロアスリートとして世界中で4、5名抱えたことです。レッドブルの支援するアスリートというのは、さまざまなスポーツの1000認単位のプレイヤーの中から厳選な審査をした上で、年間に1人、二人というレベルで決まるものなんですが、3、4年前に、ストリートファイターのプロだけで3人採用されたんです。日本、アメリカ、フランスで一人ずつです。こんなふうにeSPORTSのプレイヤーに対して、グローバルに、アスリートと同じように判断する企業は、ここ3年くらいでとても増えてきたと思います。
【後編】につづく
(構成・文/津田秀晴)