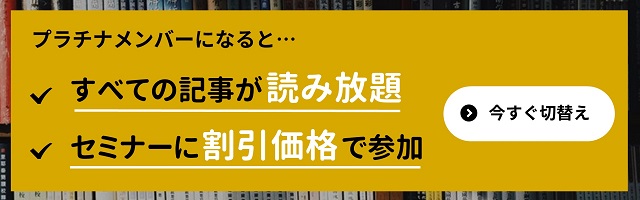2017/02/27
1/1ページ
スペシャルコラムドラッカー再論
第63回
「我々の事業は何か」を、いつ問うか。
- マネジメント
- 井上 和幸 株式会社 経営者JP 代表取締役社長・CEO
「どんな商品であればお客様は購入してくれるのか」「どんなサービスの強化を図れば、もっと売れるのだろう?」、四六時中頭の中は自社の商品・サービスのことで一杯だ。
しかし案外、「当社の事業は何か」を考えていないのかもしれない。
我が社の事業は何か、何であるべきか、を真剣に考えるのは、自社が苦境に陥ったときだけだとドラッカーは言う。
「ほとんどのマネジメントが、苦境に陥ったときにしか、「われわれの事業は何か」を問わない。もちろん、苦境時にはこの問いかけをしなければならない。事実、そのようなときに問いかけるならば、めざましい成果をあげ、回復不能に見える衰退すら好転させることができる。(中略)しかし自ら苦境を待つことは、ロシア式ルーレットに身を任せるも同然である。マネジメントとしてはあまりにも無責任である」(『マネジメント–-課題、責任、実践』、1973年)
とくにこの問いは、あなたが個人事業主ではなく、組織としての事業を営み、一定以上の市場を獲得しにいこうと思うならば、事業の構想時から行わなければならないとドラッカーは諭す。
それが自社の存在価値を明確にし、独自性をもたらし、組織として働く従業員たちを束ねるからだ。
そして改めて、ドラッカーは強調する。「「われわれの事業は何か」を真剣に問うべきは、むしろ成功しているときである」と。
「成功は常に、その成功をもたらした行動を陳腐化する。新しい現実を創り出す。新しい問題を創り出す。「そうして幸せに暮らしました」で終わるのは、お伽噺だけである」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)
そう、確かに、映画やドラマなら「ハッピーエンド」で終われるが、我々は、さらにその先も「話」は続くのだ。
もちろん、成功しているときに「われわれの事業は何か」を改めて問い直すことは容易ではない。「事業は明白であり、議論の余地はないとする。けちをつけることを好まず、ボートを揺るがすことを好まない」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)。
ドラッカーはここで、1920年代に栄華を極めていた炭鉱業、鉄道業を挙げる。
ご存知の通り、その栄華はその後、石油産業、航空業に座を奪われ衰退することとなった。
「いずれも神が独占を与えてくれたものと考えていた。事業が何かはきわめて明白であって、何も考える必要はないと思っていた。しかし、それぞれのマネジメントが、「われわれの事業は何か」を考えておきさえすれば、いずれもあのような凋落は経験せずにすんだはずだった」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)
そう、当時の炭鉱業会社が「わが社の事業は求められるエネルギー源を供給することである」と考え、鉄道業会社が「わが社の事業は人と物を適切に輸送することである」と考えていれば、自らイノベーションを起こし次の時代にも適応できたはずだろう。
同じことを私たちは、ネット回線や携帯市場で目の当たりにしていきている。
「マネジメントたる者は、当初目標としていたものが達成されたときこそ、「われわれの事業は何か」を問わなければならない。それがマネジメントの責任というものである。この責任を無視するならば転落あるのみである」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)