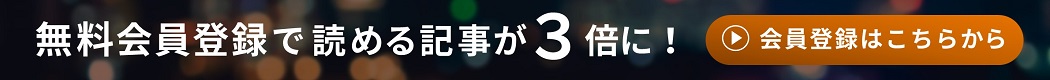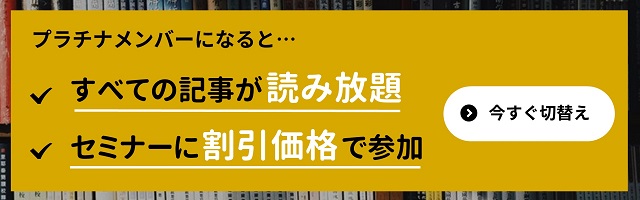2022/09/29
1/3ページ
2030年に向かえ! リーダーのためのキャリアメイク戦略
第41回
「経営者力診断」を活用して自分の現状を把握する。
- エグゼクティブ
- キャリア
- 転職
- 井上 和幸 株式会社 経営者JP 代表取締役社長・CEO
Q&A
Q:ストレングスファインダーにおいては、強みを伸ばすための行動が重要になると思いますが、経営者力についても同じでしょうか。それとも弱点を補強することを優先すべきでしょうか。
A:結論を言うと、両方大事だと考えています。強みを伸ばすことに優先度を上げていただいてもいいと思いますが、弱みを放置したままでも良くないと経営力診断は考えています。程度問題と、発揮する場所によるということはあると思いますが、お話を聞いていただいてわかる通り、構造的にいえば概ね5つの力が一定以上あることが望ましいということになっていますので。ただパーフェクトにすべてが思考・行動できるということは、誰しもありませんので、それは凸凹があってもいいと思うんですが、負っている役割とどういうような職務、企業ステージにいらっしゃるかということで重みも変わったりしますので、細かいところでご興味があれば個別にご質問いただければと思います。
ストレングスファインダーは、自分のタイプを知る意味で非常に有益だと思います。受けてみると納得性も高いと思います。強い部分をクリアに教えてくれるので、そこを認識して活かしていけば自分にとってもハッピーです。
Q:ビジョンの創造力が高く、戦略策定と組織形成が低いと診断されました。事業に落とし込むためのアドバイスなどをいただければと思います。
A:いくつかの質問項目にも出ていましたが、落とし込むために取り組むことでいうと、1つは改めてご自身が携わっている事業や商品・サービスについて、構造や仕組みなどについてもう一段、二段理解を深めてみるということ。要するにたどり着くべき先を知るということですね。それにプラスして、診断結果からすると構想力のところは長けていらっしゃるので、それを落とし込むときに一人で落とし込まなくてもいいので、関連する方々と会話をする量を増やす。ディスカッションしてみる。自分はこう思うがどうだろうと、そこでぶつけてみてフィードバックをもらう。いきなり正解を言う必要はないと思うので。すり合わせをしていきながら「こういう形ならこの構想は現場に納得性がありそうだな」とか「こういうものを求めていそうだな」といったことを、想像するだけでなく関連する人たちと話しをしながら詰めてみる。そういうことをすれば、ちゃんと落とし込まれると思いますので、そのあたりから取り組んでいただけるといいと思います。
Q:決める力で不確定要素が多い環境下、すべての情報を集めて決めることはできないと思います。
A:独善的な決定にならざるを得ないということですよね。おっしゃる通りの環境は、どの方も多いと思います。抽象的な言い方になってしまうかもしれませんが、経営や事業はすべての情報を集め切ることはできません。よく孫正義さんがおっしゃっているのは、「まあせいぜい7割方、ある程度のことが理解できたらもう決めるんだ」ということで、相関的な意味でいうとそういう感じは僕にもあります。集めすぎるのも良くないですよね。集めすぎても決められないですから。だがら、自分なりにアンテナを張ったり、関連する事業の方々や経営者の方々と情報に関してはもちろん集めてみるが、おおよそこういうことじゃないかと当たりがつくぐらいの素材が一定程度集まったとすれば、その中でどういうリスクを取りながらどう考えていくのかということです。数値的には全部お話しきれませんが。集めて客観的に見ようという意識、行動は大事です。ただそれがパーフェクトに集まることはないので、それぞれの環境の中で決めていこうというのがリーダーに求められるかと思います。
Q:以前コーチングの研修を受けたら、アナライザー、サポーター、コントローラー、プロモーターにタイプ分類される中のサポーターになりました。おそらく経営者のタイプではなく、ミドルマネジメントから幹部クラスの類型ではないか。経営者に成長していく上で、こういった人材類型と経営者のタイプ、辣腕型、カリスマ型など関連があればコメントください。
A:かなり括ってお話をしますと、サポーターの方が経営者にならないということはないと思います。経営者とは問いを立てる方です。問いを立てるときに、自分がプロアクティブに動いて行かれるタイプの方が多いんですけれども、一方でいろいろな知恵をマネジャーの方から集める。いろいろなオプションプランをもらう。最後にその中からトップとして決める。だから、サポータータイプの方が経営者としてやらなければいけないときは、サポーティブでいいと思うんですね。いろいろな現場の方に権限移譲もしながら、主体的に取り組んでもらって、いろいろな知恵を出してもらう。ただ1つだけ、サポータータイプの方がトップであればやらなければいけないことは、ご自身で決めることです。決断力のところで、最後はみんなの声をもらったうえで、右に行くべきか、左に行くべきか決断する。この最後のジャンプはトップとして決めていく。その決断力がサポータータイプについては、ひと頑張りが必要なのかもしれません。
最後に井上からひとこと
今日の組み立てとして、幹部人材と経営人材というところから切り出してお話をしました。繰り返しになりますが、ミドルマネジメントの方々は、けっして問いを立てる必要がないということではありません。ただ役割分担的にいうと、しっかり経営の側から立てた問いに対して、結果を出していくというところに重きがありますから、そこの観点でいうと実行するということと、リーダーシップが重要だということです。経営クラスの方にとっては、方向付けをしていく責務が高くなりますので、その観点で描く、決めるというところが重要になります。
あとは職種ごとでも、5つの力でこの職種はこの部分が強いとか、そういったものはありますよね。たとえば現場型で営業のマネジメントでリーダーシップを発揮している方だと、行動力であったり、やり切る、まとめるというところが強い方が多いと思います。戦略系の部署をずっと歩いてきた方ですと、どちらかというと描く力的なところに落ちてくるものが要素として求められることが多かったりもしますから、ご自身の認識を含めてそのへんが強いなと思っている方が多いのではないでしょうか。
上がり方と職務で順番はあっていいんですよね。もし皆さんが事業を最終責任者として率いていくという観点を目指す、もしくはその任務にあるという方であれば、今日お話しした5つの力は総じて平均以上には求められる立場なので、そんなふうに考えていただければいいのではないかと思います。
(構成・文/田中宏明)