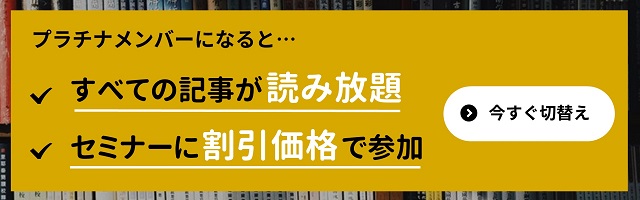2017/10/30
1/1ページ
スペシャルコラムドラッカー再論
第96回
企業自らが社会に与えるインパクトの責任と、その予測の難しさ
- エグゼクティブ
- マネジメント
- 井上 和幸 株式会社 経営者JP 代表取締役社長・CEO
「組織が社会に与えるインパクトには、いかなる疑いの余地もなく、その組織のマネジメントに責任がある。それはマネジメントが対処すべき問題である。(中略)自らが与えるインパクトは自らに責任があるがゆえに、極力小さくしなければならない。自らの目的とミッションでないインパクトは小さいほどよい。そのとき初めて責任を果たしているといえる。市民、隣人、貢献者たりうる。」(『マネジメント–-課題、責任、実践』、1973年)
事業の目的ではない副産物としてのインパクトは、最小としなければならない。許されていたとしても、いずれそれは市民の怒りとなり、対処しない企業の無神経さに対して大きなクレームや忌避となって襲い掛かることになる。
ドラッカーらしい言い回しだが、要するに、ここでドラッカーが言っている「インパクト」とは、例えば商品の安全基準に対するリスクであったり、工業生産活動の結果として排出される公害物質問題であったりということである。
我々は、こうした間接的にもたらされる影響も含めて、冷静かつ現実的に自らが社会に及ぼすインパクトを予測する必要があるのだ。
「この場合問うべきは、「われわれがしていることは正しいか」ではない。「われわれがしていることは、それに対して社会や顧客が代価を払っているものか」である。」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)
もしもこの問いに対する答えがノーであるならば、その活動はインパクトに過ぎず、したがって行うべきものではないという判断を下さなければならないのだ。
これは、言うは易しいが、実際にやるとすれば、実行は非常に難しい。特に難しいのは、技術予測に基づくインパクトの予測である。
昨今の話題のひとつは、AIがいま存在する仕事のおよそ半分を10年以内に奪う、というものだが、それは真実だろうか。あるいは逆に、半分程度で済むものなのだろうか?
「いかなる技術が重大なインパクトをもたらし、いかなる技術が単なる技術の変化に終わるかを予見することは、さらに難しい。技術の予言者として名高いジュール・ヴェルヌは、100年前に20世紀の技術の多くのものを予測した。しかし彼は、それらのものが社会と経済に与えるインパクトについては一切予測することなく、ヴィクトリア朝中期の社会と経済が永遠に続くものとして考えていた。逆に経済と社会の予言者たちの技術予測の成績たるや、無残というべきだった。」(『マネジメント–-課題、責任、実践』)
ドラッカーは、『マネジメント』執筆当時、アメリカの下院事務局が設置した「テクノロジー・アセスメント局」なる機関を指して、「テクノロジー・アセスメント局の唯一の成果は、五流のSF作家に完全雇用を保障するくらいのこととなろう」と揶揄した。
そして、それはその後、概ねその通りとなった。