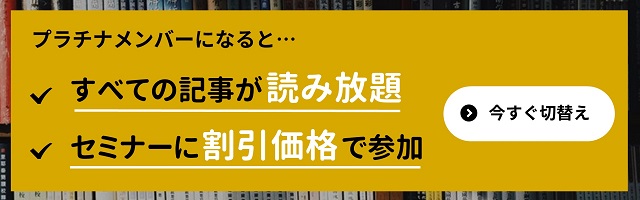2020/08/06
1/1ページ
私が経営者になった日
第40回
【貝印 遠藤氏】レールが敷かれることを「幸せ」に感じて。(Vol.1)
- キャリア
- 経営
- 経営者インタビュー
- 遠藤 宏治氏 貝印株式会社 代表取締役社長
30日無料!全記事読めるプラチナメンバー登録はこちら >
社長に任命された日=経営者になった日ではありません。
経営者がご自身で「経営者」になったと感じたのは、どんな決断、あるいは経験をした時なのか。何に動かされ、自分が経営者であるという自覚や自信を持ったのでしょうか。
カミソリ、包丁、ツメキリ、ハサミをはじめとする「KAIブランド」の商品の生産を担う「カイインダストリーズ株式会社」、その製品を販売する「貝印株式会社」を中心に、開発、生産、販売、物流の一貫体制によって、国内及び海外にも広く「KAIブランド」を展開する創業112年の老舗、貝印株式会社 代表取締役社長 遠藤宏治氏に3回にわたってお話をうかがってみました。
【vol.1】レールが敷かれることを「幸せ」に感じて。
【vol.2】「人」を中心に、自分はどう考え決断するのか。
【vol.3】KAI FAMILYとしての新しい時代を。
●創業112年の老舗の3代目として。
「敷かれたレールというのは、今になってみれば“ありがたいな”と思うことが多いですけれども、若い頃には自分はもっと能力がある、という思いもあったことは事実です。」創業112年の老舗の3代目として、様々な新しいチャレンジをしてきた遠藤氏だが「違う世界を見たい」と思ったことが何度かあるという。
「学生のときも、“違う道もあるのではないか”と思いましたし、就職のときも“全く関係のない会社に入ってみたい”ということも考えました。」
しかし、そのたびに家庭の環境でレールが敷かれているということの「幸せ」を感じて、結局は元に戻ったという。「幸せ」とはどういうことだろう。
「家業として、こういうものをやっていくことがある意味では当たり前だという、考え方をずっと小さい頃から持ってきました。だから、その枠から出ようとするのであれば、いったん立ち止まって自問自答せざるを得ない。自分はそこまでの人間なのかどうなのか、能力があるのかどうなのかと。問いを常に自分に向けることが、結果的に、与えられた環境の中で自分の能力を最大限に発揮し成長することにつながってきた。それができる“幸せ”に気づくようになれたということでしょうか」

●「もの作り」と「営業」の視点を学んできた。
地元の進学校から早稲田大学に進学、さらにアメリカの大学院に留学し経営学を学んだ。帰国後2年間は、貝印とも取引がある大手文具メーカーコクヨに勤めた。「そこで営業の第一線として2年間、修行させていただいたんです。コクヨさんは当時の貝印より大きな会社でしたが、それぞれの部署の人たちがどう考え、どう関わりあって仕事をしているのかを学ばせていただきました。そして、自分が現場の第一線で、同僚や上司と、どう思ってどう感じて仕事をしているかという体験もさせていただいて、貝印へ戻って来たわけです。」
貝印では、生産管理、工場からキャリアを始め、もの作りと生産の考え方を学んだ。
「貝印では主に生産・企画・管理をやってきて、社長就任の2年前に、初めて営業本部担当の副社長になりました。もの作りへのこだわりがある生産の側の考え方、お客様との最前線にある営業の視点の両方を、会社は違うけれども見られたというのは、経営者になる上でも良かったなと思っています。」
●「田舎の中堅企業」を垢抜けさせよう。
小さい頃から「この会社を継ぐんだ」と意識していた会社と、実際に外の会社を経験して、いざ、そこに戻ってみたときに遠藤氏の目に見えたものには、違いはあったのだろうか。「貝印は歴史はありますが、言ってみれば田舎の中堅企業だったんです。少し自虐的ですけど、結構やぼったかった。そこらへんをどう垢抜けさせていくのかということは、外から戻って最初に意識しましたね。
我々のルーツは軽便カミソリ、ブリキのカミソリで、どちらかというとおじさんの使う物、もしくはL型の日本式のカミソリで、おばさんの使う物というイメージ。だからどうしても『地方の垢抜けない企業』というイメージがあったんですね。
私が入ったときにも、いい製品は作っている。でも、我々の特徴を生かしたかたちで、もっといい物を作れる。もっと垢抜けたものができるのではないかという、思いがありましたね。」
●『親父は親父、自分は自分』
貝印に戻って7年間。“いずれ後を継ぐのだ”という意識で、CIや、いろいろな企画、経営企画をやっていた。しかし、そのときにはまだまだ社長という立場になって、どう人を動かすかという視点では仕事は進めていなかったと遠藤氏は振り返る。「当時の社長である父が病弱でしたので、私が父の代わりを務めている部分も結構ありましたが、番頭さんも、幹部さんもいましたし、体は弱くても、父には人を動かすという力がとても強くありました。
私が社長になったときには、もう父はいませんでしたから、自分でやっていかなければならなかった。自分しかいない中で、人を動かすことに優れていた父と自分とをどう比較するか、という考えを持っていなかったので、ある意味、それも恵まれていたかなと思います。
今になってこういう境地にはなったんですけれども、『親父は親父、自分は自分』だと。要はそういうことなんですよね。もう、生きる時代も違うし、時代背景も違うし、一緒に仕事をしている社員の考え方も違うし、自分自身の価値観も違うし、時代の価値観も違うので比べてもしょうがないと。それは超えられるものでもないし、超えたいと思うものでもない。逆に言うと、最初からあまり感じなかったというのは、私としては幸せでしたね。」
(構成・文/阪本淳子)