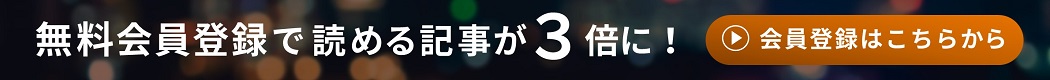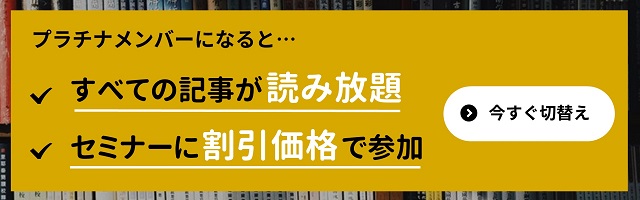2023/01/18
1/1ページ
成功する経営者は皆、多読家。「TERRACEの本棚」
第161回
言葉のセンス=教養×状況を切り取る能力/教養のある人がしている、言葉選びの作法
- ビジネススキル
- 組織
- 経営
- 岩川 実加氏 株式会社ぱる出版 編集部
60秒で簡単無料登録!レギュラーメンバー登録はこちら >
成功する経営者は皆、多読家。「TERRACEの本棚」では、成功している経営者が注目している、読んでいる書籍をご紹介してまいります。
今回は、『教養のある人がしている、言葉選びの作法』。本書の編集を手掛けられた、株式会社ぱる出版 岩川実加氏に見どころを伺いました。
こちらは会員限定記事です。
無料会員登録をしていただくと続きをお読みいただけます。