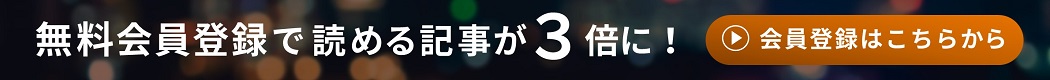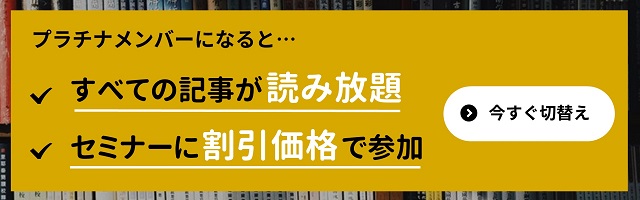2021/11/18
1/2ページ
イマ、ココ、注目社長!
第192回
これまで思っても言えなかった多様な価値観が事業に。【前編】
- 注目企業
- 組織
- 経営
- 経営者インタビュー
- 大瀬良 亮氏 株式会社KabuK Style 社長/共同創業者
60秒で簡単無料登録!レギュラーメンバー登録はこちら >
定額制宿泊サービス「HafH(ハフ)」の運営、宿泊及び賃貸運営業、旅行業を展開するKabuK Style(カブクスタイル)。一人ひとりが多様な価値観をそのままに選択できる、傾く《かぶく》生き方ができる未来を創るために邁進しています。「旅しながら働く」生き方をサブスクで提供する、社長/共同創業者の大瀬良亮さんに伺いました。
こちらは会員限定記事です。
無料会員登録をしていただくと続きをお読みいただけます。