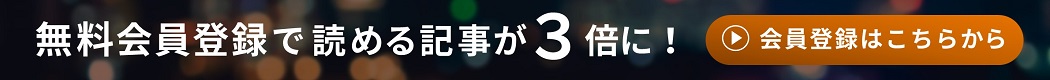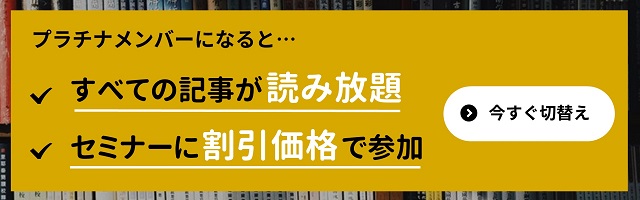2021/03/30
1/1ページ
エグゼクティブの思考をDoubRingで可視化する
第10回
「才能と努力」 ー結果と解説ー
- エグゼクティブ
- ビジネススキル
「DoubRing」で仕事や生活に関する様々な関係性を考える、その第5回のテーマはある意味で全ての人にとっての「永遠のテーマ」と言える「才能と努力」です。
「才能か努力か?」という問いは教育現場のみならず、ビジネスの現場でも頻繁に話題になったり自問自答したりするものではないでしょうか?
特にビジネスの場面においては、高い業績を上げたり早く昇進したりといったパフォーマンスを上げる「ハイパフォーマー」と、その逆の「ローパフォーマー」の差がどこから生まれ、どうすればハイパフォーマーを増やせるかというテーマは常に人材の育成や目標達成といった場面で話題に上ることかと思います。
「あの人は生まれながらに才能を持っている」
「そんなこと言っていても仕方がないから自分にできる努力を最大限にしてみよう」
「入社してから育てることに時間や労力をかけるより、才能を見抜いて素質がある人を採用することに注力すべきだ」
「努力しても数字や結果に現れなければビジネスにおいては意味がない。だから結果が全ての評価制度を作るべきだ」
「才能があることに慢心する『うさぎ』もいれば、逆に自分に才能がないからこそ努力してパフォーマンスをあげる『かめ』もいるから、努力が正当に評価される制度を構築すべきだ」
こんなやり取りが日々社内で行われているのではないでしょうか?
今回のサーベイではその「才能と努力」の関係について、DoubRingの手法で75名の方から有効回答を得ました。
(※DoubRingの詳細について知りたい方はこちらを参照下さい)
こちらは会員限定記事です。
無料会員登録をしていただくと続きをお読みいただけます。