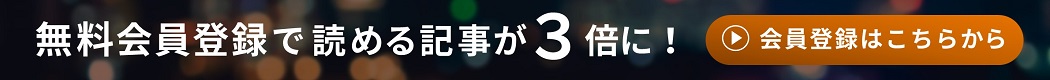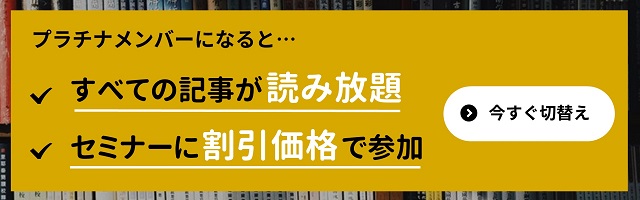2019/03/15
1/4ページ
理論で固める経営戦略
第17回
“細胞”の集合体のような組織 ーー“アメーバ経営”との類似性
- 経営
前回は、ティール型組織の形態イメージとマネジメントチームのメンタルモデルに焦点を当てて、パラダイム・チェンジの方法論を述べてきた。今回はティール型組織の特徴を、日本発の「アメーバ経営」との類似性で考察していく。これによって、日本企業はティール型組織を取り入れやすくなるかもしれない。
■7つのパラダイム

こちらはプラチナメンバー限定記事です
プラチナメンバー登録(年間11,000円or月間1,100円)を
していただくと続きをお読みいただけます。
※登録後30日間無料体験実施中!